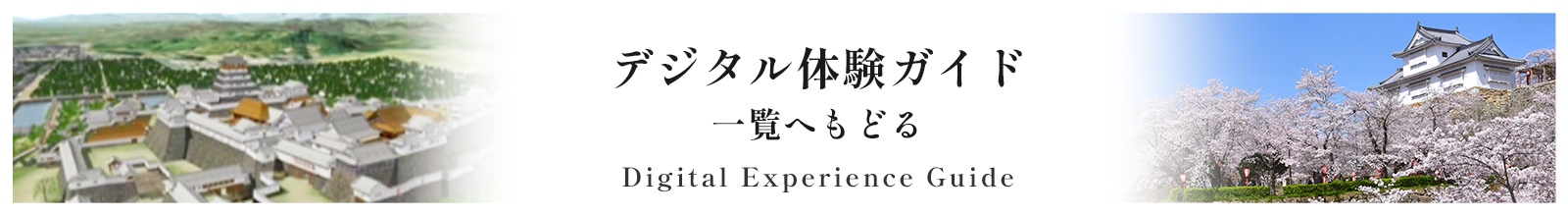解説津山城

【津山城跡】
本能寺の変で織田信長と運命を共にした森蘭丸の末弟森忠政は、今から約400年前、美作国(岡山県の北部)の大名となり、1604年( 慶長4年)から1616年(元和2年)まで、足かけ13年の歳月を費やし、津山城とその城下町を建設しました。
津山城は、「鶴山(つるやま)」と呼ばれ る山の最高所に天守と御殿を持つ本丸を築き、二の丸・三の丸と山全体を三段の石垣と9 0棟以上の櫓と城門で武装した城郭です。 この城の主は、森家が四代続きましたが、その後徳川将軍家の一族である松平家が引き継ぎ、明治維新を迎えました。 城内の建物はその後すべて撤去され、石垣しか残っていませんでしたが、2005年(平成 17年)には備中櫓が往時の姿に復元されました。 城跡は現在「鶴山公園」として、桜の名所としても親しまれています。
【天守】
津山城のなかで最大規模の建物で、津山城・津山城下町のシンボルであるのが「天守」です。外観五層、内部も五階建てで、外部には破風などの装飾を全く持たないシンプルな外観ながら、鉄砲狭間が101ヶ所、矢狭間は59ヶ所もあり、その高さは22m、さらに高さ6mの石垣の上に建てられており、正に「シンボル」にふさわしい威容を誇っていました。この天守は本丸の西端に建てられており、本丸からは石垣と二か所の門で区切られており、いざという時には天守周辺のみで籠城することもできる設計となっていました。 天守最上階には、細川ガラシャの夫で小倉城主の細川忠興から送られた洋風の南蛮鐘が吊り下げられていました。

【備中櫓】
数ある城内の櫓の中で天守に次ぐ大規模な櫓で、本丸から南に張り出して建てられており、城下町を横断する「出雲街道」からもよく見える櫓であったと絵図等に伝えられています。幅24m、奥行き8m、高さ13mの二階建の建物で、屋根は本瓦葺、壁は白漆喰塗、窓には格子を入れ、矢狭間・鉄砲狭間で武装した櫓でした。一方内部は全て畳が敷き詰められ、10室に区切られていました。この櫓は、藩主の居間から渡り廊下を通ししか入ることができないため、藩主の家族の私的な生活空間であったと考えられています。特に絵図面には壁が「唐紙」と記されており、おそらく藩主の家族の女性が暮らしていたものと思われます。 「備中」という名前は、築城主森忠政の 娘「お松」が嫁いだ「池田備中守長幸」に因むと伝わります。

【津山城の堀と門】
織田信長の家中で「攻めの三左」の異名を持 つ森可成の子で、本能寺の変で長と運命を 共にした坊丸・力丸・蘭丸三兄弟の弟でもある森忠政は、1603年、美作国一国186,500石を与えられ、足掛け13年の歳月を費やして津山城及び城下町を建設しました。 吉井川の北側の独立丘陵である「鶴山」を中心にして城を築き、東側は宮川を堀に見立 て、北・西・南側は堀と土塁で防を固め、城の内外を六か所の門で仕切っていました。 城内と場外は土の橋でつながれていましたが、この京橋門の部分は城の大手口であり、格式の高い木の橋がかかっていました。さらに門の両側には石垣が築かれ、容易に城内に侵入できないようになっていました。

【表中門】
城内の三の丸から二の丸に至る登城路の正面 にあるのが「表中門」です。二階櫓の一階が門 になった「櫓門」です。 過去の発掘調査により、柱の下に据える「 礎石」が確認され、門の構造と規模が判明し ています。その規模は長さ32m(16間)で、城内最大規模のみならず、江戸幕府が築いた城 郭以外では日本最大級の櫓門です。 一般的に城の通路は大勢の敵に攻め込まれ ないように比較的狭く作られますが、この部 分の通路は例外的に大規模で、築城主の森忠 政の防への自が表れています。礎石の一部は現地に露出しており、実際に 見ることが可能です。

【表鉄門】
表鉄門は、本丸への入口にある櫓門で、門扉全体が鉄板で覆われていたことに由来します。門をくぐると、石段があります。石段を登り、180度方向をかえると、そこに本丸御殿の玄関があります。この玄関は、表鉄門二階にあたります。玄関の石段をのぼると、式台と呼ばれる部屋があり、「広間」へ続きます。さらに進むと「旗竿の間」、「鑓の間」と続き、御殿の大広間につながります。表鉄門は城門としてだけでなく、本丸御殿への正式な入り口としての役割も持っていました。文化6年(1809) の火災により、本丸殿のすべての建物及び表鉄門、裏鉄門などは焼失しています。東側にある石垣を観察すると、熱を受けて赤く変色した石を確認できます。

【本丸】
津山城の最高所は「本丸」と呼ばれ、中央の広場に広大な本丸御殿があり、その周辺には天守や櫓が林立していました。御殿は藩主が公的な行事を行う「表御殿」と、日常生活を営む「奥殿」に分かれていました。表殿の部屋は、襖に描かれた絵によって「皇帝の間」「松の間」「紫陽花の間」などと名前が付けられており、奥殿の部屋は、居間として「御座之間」、寝室として「御寝之間」などと機能によって名前が付けられていました。御殿は津山藩の「役所」の機能も兼ね備えていたため、たくさんの部屋が必要とされていました。そのため、本来は倉庫として使われることの多い「櫓」の内部も「本丸御殿」として利用し、必要な部屋数を確保していたようです。