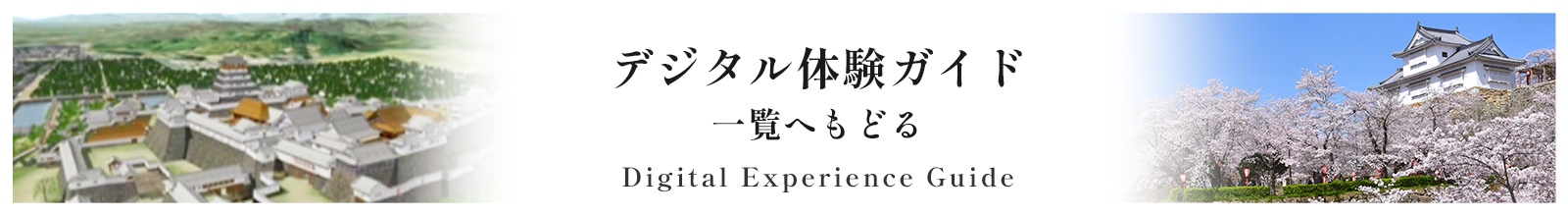衆楽園
津山藩の奥座敷回遊式庭園。
浮島と水面に映る島影、陰影に富んだ樹木の枝ぶりなど、その幽玄な景観に、時の経つのを忘れる

名勝旧津山藩別邸庭園「衆楽園」は江戸時代初期の大名庭園です。
津山城の北方約500mに位置し、江戸時代には、東西300m、南北300mの規模であったと言われています。遠方の山々を借景に取り込み、敷地の過半を占める池泉を島によって4つに仕切り、その周囲を回遊する構成となっています。
庭園は南北に長い池が敷地の大部分を占めており、その池を分けるように四つの島が配置され、北から霧島・中島・浮島・紅葉島と呼ばれています。
中島は両岸と土橋で繋がっており、北端には清涼軒が建てられています。
浮島は元は東岸と陸続きでしたが、現在は独立した島となっています。

北から導かれた水は重畳する深い築山の間を流れ、小さな滝を経て池へと導かれます。滝石組は本庭園の中でも江戸期の様相をよく残している部分であり、北側の主要な景観を形成しています。
落ちる水に変化を付けるため、水落の一枚岩の上面に等間隔の刻みを数箇所入れるなど、独特の技巧が見られます。

園内北東部に配置される延長210mに及ぶ曲水は、江戸時代の絵図にはみられない施設です。
文献には明治3年に津山藩最後の藩主松平慶倫の子康倫によって「曲水の宴」が開催されたという記述がみられることから、この頃につくられたものと推測されます。
現在もこの施設を利用して、津山出身の新興俳句の鬼才西東三鬼に因んだ「曲水の宴」が開催されています。

余芳閣は明治期の古写真で確認できますが、現在の建物が江戸期のものを残しているかは不明です。
迎賓館は古い絵図に記載されている場所に明治30年に新築されたものですが、老朽化が進んだため撤去されました。現在の迎賓館の建物は昭和45年、市内京町にあった旅館「対鶴楼」の2階部分を移築して建てられたものです。