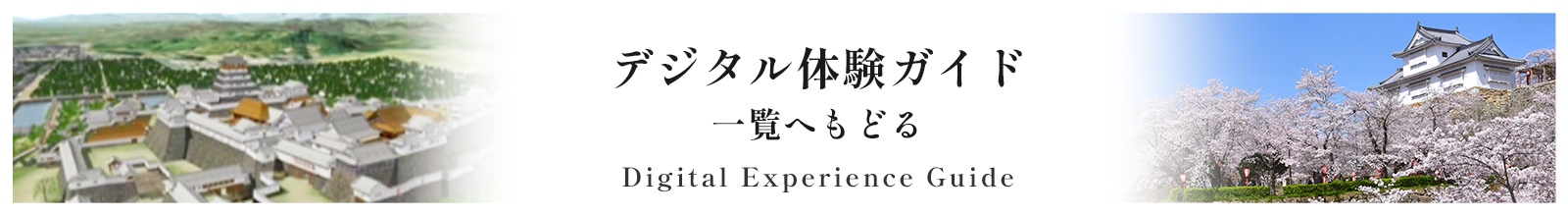箕作阮甫旧宅
博覧強記のルーツを訪ねる。
津山藩医であり、洋学者として学問の発展や教育に多大な影響を与えた箕作阮甫の生家

箕作阮甫旧宅は津山城の東にのびる出雲街道に面した城東重要伝統的建造物群保存地区に位置します。建物は江戸時代中期、1700年代の建築と考えられています。
城東地区では珍しい平屋の建物で、元々は隣家と壁一枚でつながっていましたが、、両隣が撤去され現状では独立した建物となっています。
柱が細いこと、垂木には竹を用いていること、屋根の勾配が非常に緩いことなどの特色があり、城東地区の江戸時代中期における小規模町家建築の典型的な建物です。

箕作阮甫は津山藩医であり、また洋学者でもありました。
阮甫は津山藩医の子として寛政11年(1799)にこの地に生まれました。
若くして父・兄を失い家督を相続した阮甫は儒学と医学を学び、京都で医術の習得に励みました。
文政2年(1819)年に津山城下で開業した阮甫は、文政6年(1823)には藩主のお供で江戸に行き、宇田川玄真の門に入り蘭学の研鑽を重ねました。
嘉永6年(1853)のペリー来航時にはアメリカ合衆国大統領の親書の翻訳を命じられ、同じ頃ロシアのプチャーチンがやってきた時は、交渉団の一員として長崎に派遣されるなど、日本の開国に際して大いにその才能を発揮しました。
開国後、本格的な洋学の研究・教育の必要性を痛感した幕府は、安政3年(1856)に蕃書調所を設立しましたが、阮甫はその教授に任命されました。
さらには当時天然痘の予防のための江戸における拠点である「お玉ケ池種痘所」の設立にも尽力しました。
蕃書調所が後の東京大学、お玉ケ池種痘所が後の東京大学医学部へと発展したことから、阮甫は「日本初の大学教授」と呼ばれることとなりました。

阮甫は近代科学の発展に大きな影響を与えた宇田川玄真に蘭学を学び、数多くの翻訳書によって西洋文化の導入に大きく貢献しました。
箕作阮甫旧宅は阮甫が文化9年(1812)に戸川町に転居するまで、人格形成期である少年期を過ごした場所として史跡に指定されています。