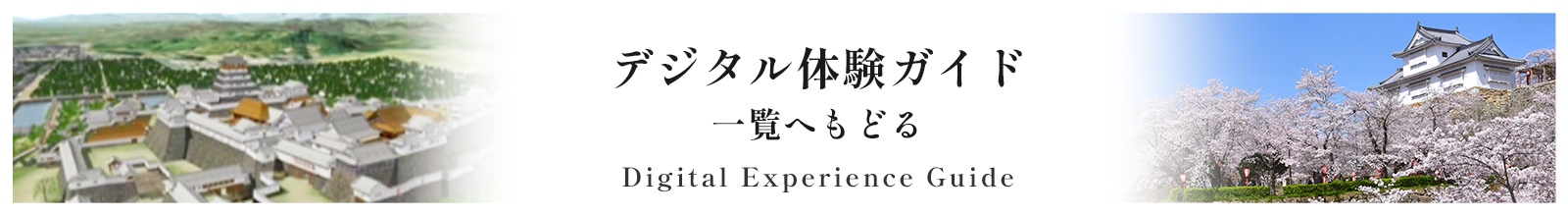城東むかし町家
江戸末期から大正、昭和初期と、時代の変遷を反映した豪商宅。
変化にとんだ意匠とともに、当時の生活様式に触れることができる。

城東むかし町家は正式名称を旧梶村家住宅といい、津山城の東にのびる出雲街道に面した城東重要伝統的建造物群保存地区に位置します。
主屋や土蔵など多くの建物群から構成されており、古いものは主屋が幕末頃の建物、新しいものは土蔵で昭和戦前期の建物です。
また、石組みの池泉庭園は水道が敷設された昭和初期の完成と考えられています。
城東むかし町家は、江戸時代から豪商として知られ、明治期に実業家として大いに隆盛した梶村家の様子を今に伝える貴重な町家建築です。

表門は大正時代の建築で、棟門と呼ばれる簡素な型式の門です。
両脇には一段高い屋根付きの袖塀が伸びており、ちょうどその真ん中に組み込まれています。
主屋は江戸時代末の建築で、間口8間半(17m)、奥行7間(14m)の大規模な町家です。
外観はつし二階建て瓦葺きの建物で、表の壁は下半分に石を貼っており、入り口の戸は垂直に上がる擦り上げ大戸となっています。
内部は東側に土間を設け、西側に部屋を配置していますが、この内装は大正時代に大改造されています。

庭園は昭和初期に築庭されたもので、池を中心に、南西隅に巨大な石で滝石組みを作っています。
滝には上水道から水が導かれ、水の流れと深山幽谷を象った景色は力強さと独特の意匠が見られます。
作庭にあたりモルタルなど当時の最新鋭の材料・工法を応用しており、この地の近代庭園文化の一端を知ることができます。

大正時代に建築された、座敷と呼ばれる主屋とつながった二階建ての大きな建物があります。
一階・二階の外面を取り巻くガラス製の建具が特徴的な建物で、内部は一階・二階ともに二間続きの広い座敷となっており、良質な材が使われ、欄間や建具などにも技巧が凝らされています。
大正時代の洗練された技術や技法を伝える貴重な建物です。

洋館・裏座敷は大正時代の建築で、洋館部分の外壁は「ドイツ壁」と呼ばれるモルタルを壁にぶつけて仕上げる特徴的なものとなっています。洋館部分の窓は上げ下げ窓、出入り口も木製のドアとなっており、外観、内部ともに典型的な洋館建築となっていますが、裏座敷と一体化しており、和洋折衷の不思議な空間となっています。