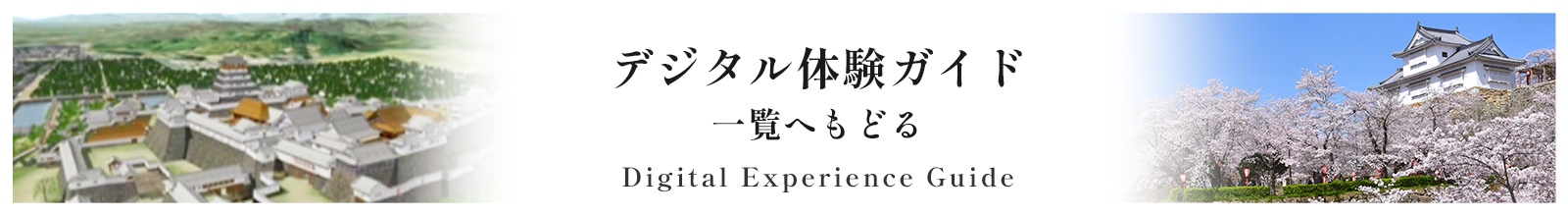津山市城東重伝建地区
津山城下町の風情を残す、情緒的なまちなみ。
江戸末期から明治時代の伝統的な建築物が軒を連ね、当時の栄生をうかがわせる。

城東地区は津山城下町の東側に位置し、面積は約8ヘクタールで東西約1.2㎞にわたり出雲街道を南北に挟むように町家が配置されています。
江戸期に発展した町並みで、主屋は切妻造平入りが原則であり、出格子窓、海鼠壁、袖壁などの意匠的に優れた伝統的建造物が街路側溝ギリギリに、建物正面の壁を立ち上げています。また建物の両側は隣家と壁を接し、あるいは共有して密集しています。
地区内を通る出雲街道は東端、中程、西端の三カ所で鍵形に折れ、街道を進む者の見通しを妨げる構造になっています。

箕作阮甫旧宅は江戸時代中期、1700年代の建築と考えられています。
城東地区では珍しい平屋の建物で、主屋、付属屋、土蔵が細長い敷地の中に整然と建築されています。箕作阮甫が、人格形成期である少年期を過ごした場所として史跡に指定されています。

旧苅田家住宅は間口14間半の巨大な主屋と7棟の土蔵群、長屋門などからなる城東地区で最大の町家です。
主屋が建設されたのは18世紀半ばで、それ以降武家地を取り込むなど敷地を拡大しながら明治期に現在の姿になりました。

城東むかし町家は正式名称を旧梶村家住宅といい、城東地区の東寄り、出雲街道北側に位置します。
多くの建物群から構成されており主屋は幕末頃の建物を大正期に大改造したもの、新座敷は明治初期、表門・座敷・洋館・裏座敷・東蔵は大正期、西蔵・茶室は昭和初期の建物です。
特に座敷と呼ばれる主屋とつながった二階建ての大規模な建物は、広範囲にガラス建具を使用して開放的な空間としており、使用材や細工などに大正時代の洗練された技術や技法を知ることのできる建物です。

洋館の外壁はドイツ壁となっており、和と洋を巧みに取り入れた意匠は地区内では他に見ることができません。
また、石組みの池泉庭園は水道が敷設された昭和初期の完成と考えられています。
近世末から近代にかけての様々な構成要素からなる城東むかし町家は近代以降に実業家として大いに隆盛した梶村家の様子を今に伝える貴重な町家建築です。

城東地区の主屋は街道沿いの敷地境界ギリギリに建物正面の壁を立て、横の壁は隣とお互いに接し、場合によっては壁を共有する形で立ち並んでいることが特徴です。さらに本瓦葺きの下屋根庇は主屋をまたいで連続し、現存最長で55m連続しており、城東地区独特の景観を創りだしています。