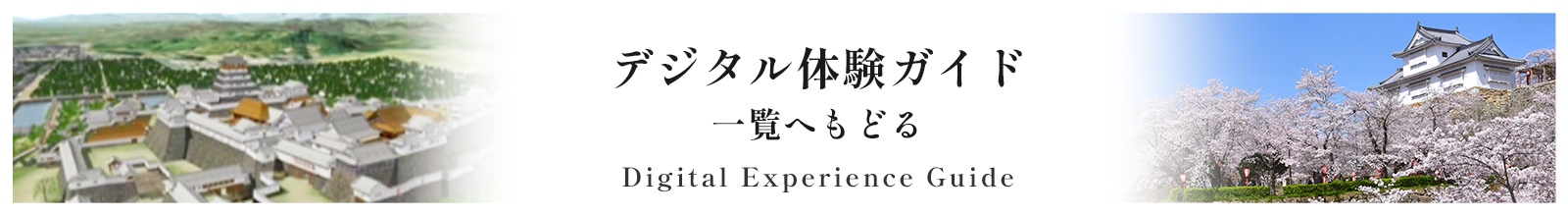津山市城西重伝建地区
津山城下の西に位置する津山の近代化を支えた町並み。
寺社、商家建築を中心に、明治、大正期のモダンな景観を楽しむことができる

城西地区は津山城下町の西側に位置し、面積は約12ヘクタールで東西に延びる出雲街道の南北に挟むように町家と社寺地が配置されています。
地区内の西側には多様な宗派からなる広大な寺町があります。各寺院の本堂の建設時期は江戸時代初期から現代までさまざまであり、現在は12か寺が伝わっています。
東側には、森忠政が城下町建設の手始めとして建設した、津山の惣鎮守である徳守神社もこの城西地区に位置しています。
また、明治以降昭和に至る町家建築が連なっています。

作州民芸館は明治42年(1909)に土居銀行津山支店として建設されました。岡山県技師江川三郎八の設計になる木造建築で登録有形文化財です。
正面左右に塔屋を配する端正な外観で、当初はより重厚な外観でしたが、大正9年に本店とするにあたり現在の外観に改装されたと考えられています。
城西地区に残る数少ない洋風建築で、明治・大正期の城西地区の隆興を示す貴重な建物です。

翁橋は大正15年(1926)に建設された鉄筋コンクリート製の橋で登録有形文化財です。橋の四隅にはアールデコ様式の欄干親柱が立てられています。また、橋の上面は全面レンガ舗装となっており、現存するものはここだけと考えられています。

本源寺は津山城下町を建設した森家の菩提寺です。元は院庄館跡付近にあった安国寺を城下町建設時に城下に移して龍雲寺と改称し、森忠政50回忌に際して本源寺と改めました。
出雲街道から北に入ると、本源寺の総門があり、さらに中門が設けられています

境内は南を正面として東から庫裡、玄関、本堂が接続して並び、本堂の西側を森家の墓所として正面に表門、奧に霊屋を配置しており、さらにその奥に歴代藩主の五輪塔が並んでいます。
特に本堂は津山城下町建設期に遡る城下で最古・最大の方丈型式の建物で、そのほか江戸時代前期から中期にかけて建築された中門・庫裡・霊屋・霊屋表門などがまとまって残っており、城西地区のみならず津山を代表する寺院と位置づけられ、重要文化財に指定されています。

寺町は江戸時代には最大24、現在は12ヶ寺が密集しており、現在でも17世紀初頭から20世紀後半の各宗派各時代の多彩な建築様式を見ることが出来ます。