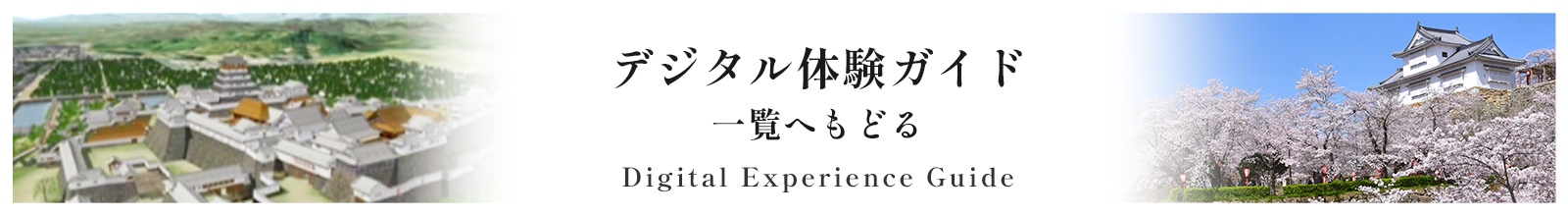津山城の歴史と魅力
丘陵より津山市内を眼下に臨み、古に思いをはせる日本三大平山城と称される城郭は、津山を代表する歴史遺産でもある。

美作国は和銅6年(713)に備前国から分割して新たに成立した国です。建国以来、津山地域は、美作国の拠点として栄えてきました。
しかし、戦国時代には、美作国を基盤とする安定した勢力が存在せず、常に周辺勢力の草刈り場となっていました。
関ヶ原以降、小早川氏の統治を経て、慶長8年(1603)美作一国186500石で森忠政が封じられ、津山城が築城されました。

津山城は、吉井川の北側の独立丘陵に築かれた城です。東側を流れる宮川を堀に見立て、北・西・南側は堀と土塁で防を固めています。
本丸・二の丸・三の丸と区切った「一二三段(ひふみだん)」という城郭形態を有しています。
城内の石垣の各所には、60を超える櫓が配置されていました。
丘陵部と平地を利用して作られた平山城と呼ばれる形式の城で、山城と平城の性質を併せ持っています。姫路城、松山城と並んで「日本三大平山城」に数えられています。

表中門は三の丸から二の丸へと進む門で、一階が門、二階が櫓となる櫓門であり、東西幅約32mと、津山城内で最大規模の櫓門です。
門の中で通路が二方向に分岐する珍しい構造を持っています。

表鉄門は本丸の入り口となる櫓門です。守りを固めるために門の柱や扉には鉄が張られていたようです。
一階部分の門をくぐって本丸に入ると、二階部分の西面が本丸御殿の玄関となる特殊な構造を持っています。

津山城には堀に面した土塁上の櫓を含めると、60を超える櫓が建てられていました。
中でも本丸の南に突出して建てられた備中櫓は城内で最大規模の二重櫓です。
備中櫓内は全室畳敷きの居室で、一階には床と違い棚を持つ御座の間や茶室、二階には二間四方の御上段が備わり、壁やふすまには唐紙が使用されるなど瀟洒な設えとなっていました。
津山城築城開始から400年にあたる2004年、当時と同じ材料・技術で復原整備されました。

本丸御殿は本丸の中央部に建てられていました。本丸御殿の東側には「表(おもて)」と呼ばれる主に儀式に使われる部分があり、次いで、「表」の西側に「中奥(なかおく)」と呼ばれる政庁に使われる部分がありました。また「中奥」の南には「奥(おく)」と呼ばれる藩主一族の居住空間がありました。
備中櫓は「奥」と渡り廊下でつながっており、「奥」の一部として使用されていました。

天守は最上層以外に破風のない五層の層塔型天守で、四層目の屋根が短く一見四層に見えます。
一辺22~24mのほぼ正方形の平面で高さは石垣含めて約28m、100を超える鉄砲狭間、70近い弓狭間を持ち、四隅には石落しを備える重武装の天守でした。

津山城は明治6年(1873)の廃城令により、天守・御殿・櫓などことごとく取り壊されました。
城跡は一時期荒れ放題となりますが、明治33年(1900)には鶴山公園として再出発、昭和38年(1963)には国史跡に指定され現在に至ります。